八佾第三(3)
[白文]3.子曰、人而不仁、如礼何、人而不仁、如楽何。
[書き下し文]子曰く(いわく)、人にして仁ならずんば、礼を如何せん(いかんせん)。人にして仁ならずんば、楽(がく)を如何せん。
先生がいわれた、「人として仁でなければ、礼があってもどうしようぞ。人として仁でなければ、楽があってもどうしようぞ。」
(礼というのは)法律と対して、それほど厳しくはない慣習的な規範。主として冠婚葬祭その他の儀式のさだめをいう。社会的な身分に応じた差別をするとともに、それによって社会的な調和をめざす。
楽 ー 音楽。礼儀と並んで人間の容儀・品性を整える。
岩波文庫 『論語』 金谷 治 訳注 岩波書店
論語では礼が大事なのかと思っていたのですが、八佾第三(3)で、孔子が上記のようなことを言っていました。
仁とはなんなのか?
仁は孔子のとなえた最高の徳目。人間の自然な愛情にもとづいたまごころの徳である。
岩波文庫 『論語』 金谷 治 訳注 岩波書店
ということで、八佾第三(3)を再度解釈し直してしてみると、
人として、人間の自然の愛情にもとづいたまごころの徳がないのであれば、礼(慣習的な規範)があってもどうしようもない。人として愛情にもとづいた真心の徳がないのであれば、音楽があってもどうしようもない。
と、孔子先生は、このようにおっしゃっているのですね。
この話は、かつて師と呼んだ人とのやりとりを思いださせます。

キクちゃんは人と付き合うときに何が大事だと思うんか?

敬意ですか?

はぁ?誠意?

敬意ですか?

なお、いけんわーや。
今思えば、師は、愛やまごころが大事だと言おうとしていたのだと思います。愛にもとづくまごころがあるからこそ、人を尊重できたり、尊敬できる点を探せる。思い出しながら、そういうものなんだなと、あらためて学びました。
師には経験を通じて、大切なことに気づかせてくれるきっかけを与えてくださり、感謝しています。
自分も愛やまごころは良いものだと思います。人や社会を信じられない時期、半信半疑の時期は長くありましたが、今思えば、それを学ぶための経験だったようにも思います。
大切なのはそこなのかなと。文面だけでなく、体験として腑に落ちる文章でした。
2025/06/12 22:03:05 キクシェル

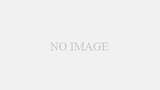
コメント