今日は、老子三十三章に出てくる言葉について考えてみようと思います。
老子三十三章
『知人者智、自知者明。勝人者有力、自勝者強。知足者富、強行者有志。不失其所者久、死而不亡者寿』
人を知る者は智なり、自ら知る者は明なり。人に勝つ者は力有り、自ら勝つ者は強し。足るを知る者は富み、努めて行なう者は志有り。其の所を失わざる者は久し、死して亡なわざる者は寿し。
『ビギナーズ・クラシックス 中国の古典 老子・荘子』 角川ソフィア文庫 野村茂夫 2020年
キクシェルさんは、こういう解説文を鵜呑みにできない性分です。なので、独自に考えてみたいと思います。
漢文のテストは0点だったので、信頼性については保障できません。ひとつの説としてご了承ください。
ここからキクシェル超訳老子三十三章を考えてみたいと思います。まずは文字の意味から生きたいと思います。
智:物事を良く知り尽くしわきまえている
明:はっきり見える 明るく光る
勝:相手を負かす 勢いが優れている
力:外に現れる働きの元 ものを動かす作用
強:勢力がある 筋力がつよい 心がしっかりしている
行:歩いてゆく 動いてゆく 旅 進む
志:ある目標の達成を目指して心を向ける
所:場所 地位 特定の仕事のために設けた場所
久:時間的に長い 長い間そのままにしてある
寿:長命である 長生きしている
足るについては、上記のサイトになかったため、下記のサイトを引用します。
古代中国語のtsjowk(足)の意味・用法には、中国の歴史が関係しています。東アジアでは、非常に古くから土器が作られ、すでに15000年ぐらい前には、様々な場所に土器が存在しました( Kuzmin 2017 )。土器も時代によって変化し、やがて3本の足が付いた土器が現れます。それに続いて、3本の足が付いた青銅器も現れます。いかにも中国らしい器です。このような器は、古代中国語でteng(鼎)テンと呼ばれました。teng(鼎)はもともと料理用ですが、祭り事で使われるうちに権力の象徴にもなりました。下肢を意味していた古代中国語のtsjowk(足)は、まずは土器・青銅器などに足を付けることを意味するようになり、そこから一般になにかを加えることを意味するようになっていったと見られます。
中略・・・・・・
昔の日本語のtaruとtasuのtaはなんでしょうか。「いっぱいある状態」を意味するtaという語があって、そのような状態になることをtaru、そのような状態にすることをtasuと言っていたと見られます。このtaはなにかというと、古代中国語のta(多)だったのです。
ということで、独自の超訳をまとめてみます。
知人者智、自知者明:人を知る者は、物事を良く知り尽しわきまえていて、自らを知る者は、物事がはっきり見える。
勝人者有力、自勝者強:人に勝つ人は物事を動かす作用があり、自らに勝つ人は心がしっかりしている。
知足者富、強行者有志:いっぱいである状態を知る人は富み、心がしっかりして動いて進む人は、目標の達成を目指して心向ける。
不失其所者久、死而不亡者寿:その仕事場を失わない人は長く、死して亡くなることがないものはさらに長命である。
『知足者富、強行者有志』
いっぱいである状態を知る人は富み、心がしっかりして動いて進む人は、目標の達成を目指して心向ける。
あらためて突きつけられたなと思います。
何がいっぱいな状態なのかというのですが、『感謝の気持ち』『しあわせな気持ち』ということかもしれません。そういう人は自然と富んでいくのだろうと思います。
自分の人生を考えてみれば、かつての自分は、全てはあたりまえに起こっていて、感謝の気持ちを持てない時があったなと思っていました。
よく考えてみれば、感謝の気持ちと、しあわせな気持ちがいっぱいなら、小さな富も大きな富に感じることができるだろうなと思います。
そして、心がしっかりして、行動する人は、目標の達成を目指して、生きていけるのだと思いました。
心をしっかりと持つために何が必要だろうか。考え、試行改善しながら行動していきたいと思います。
これからも、感謝の気持ちと、しあわせな気持ちを大切にして、人生を生きていきたいと思います。
2025/01/13 20:47:32 キクシェル

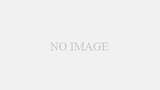
コメント