論語の最初なのですが、以下のような文があります。
学而第一(1)
子曰、学而時習之、不亦説乎、有朋自遠方来、不亦楽乎、人不知而不慍、不亦君子乎。
先生がいわれた、「学んでは適当な時期におさらいする、いかにも心嬉しいことだね。(そのたびに理解が深まって向上していくのだから。)だれか友だちが遠い所からもたずねて来る、いかにも楽しいことだね。(同じ道について語りあえるから。)人が分かってくれなくとも気にかけない、いかにも君子だね。(凡人にはできないことだから。)」
訳 岩波文庫 『論語』 金谷治 訳注 岩波書店
この、『学びて時に之を習う』というところなのですが、安岡正篤先生の『論語に学ぶ』という本では、『時』は時々ではなくて、『その時代、その時勢に応じて』と訳せばよい、ということでした。
折に触れて何度も復習することはもちろん、社会の時代や時勢に応じて学ぶ必要があるのだな、と解釈しました。
それを受けて、この論語を読み始めて、ひっかかるところもあるな、という印象がある部分もありました。
里仁第四(18)
子曰、事父母幾諌、見志不従、又敬不違、労而不怨。
先生がいわれた、「父母に仕えて(その悪いところを認めたときに)はおだやかに諫め、その心が従いそうにないとわかれば、さらにつつしみ深くしてさからわず、心配はするけれども怨みには思わないことだ。」
訳 岩波文庫 『論語』 金谷治 訳注 岩波書店
親や年長者のあやまちを穏やかに諫め、本当に物事がよい方向に向かうのかどうか、ということ。
論語では孝行悌順(こうこうていじゅん)(孝は父母によく仕えること、悌は兄や年長者によく仕えること。)が言われますが、経験から、年長者がおかしかったら、よく仕えたら間違った方にいくのではないかと思うのです。そのあたりのことは、仁の徳のある年長者だったらという条件つきなのではないかと思います。
まだ、全てを読み終わったわけではないですが、「孔子の道は一つのことで貫かれている」というようなことが描かれている部分がありました。
里仁第四(15)
子曰、参乎、吾道一以貫之哉、曾子曰、唯、子出、門人問曰、何謂也、曾子曰、夫子之道、忠恕而已矣。
先生がいわれた、「参(しん)よ、わが道は一つのことで貫かれている。」曾子は「はい。」といわれた。先生が出てゆかれると、門人がたずねた、「どういう意味でしょうか。」曾子はいわれた、「先生の道は忠恕(ちゅうじょ)のまごころだけです。」
忠とはうちなるまごころにそむかぬこと。
恕とはまごころによる他人への思いやり。訳 岩波文庫 『論語』 金谷治 訳注 岩波書店
孔子の弟子の発言ですが、忠恕はとても大切なことだとおもいます。
私が着目したのは、「わが道は一つのことで貫かれている」というところです。
今回もここで、考えてみました。
自分の道は何で貫かれているかなと。
立派なものではないだろうな、という気がします。いくつもの道を選べずに分岐していく道に、分岐するごとに迷い、恐る恐る進んできたというのが実態です。
今は、道というよりは開けた場所を歩いている状態の感覚があります。
遠くに見える街(予祝したイメージ)を見ながら、一歩一歩、歩いているという感じです。
まだ形になっていない道が、自分の後ろに足あととしてできているイメージです。
それが、もしかしたら、わが道を行くというか、そういうことなのかなと思いました。
話はずれたかも知れませんが、論語を読みながら、浮かんでくることは(教義に関することではなくても)あります。自分は聖人君子でもありませんので、論語を読みながら浮かんでくる、そちらの方も大事にしたいと思っています。
2025/06/10 05:03:07 キクシェル

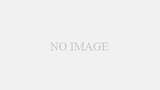
コメント