先日、『何か間違っている』と題した記事を書きましたが、新たな発見がありましたので記載しておきます。
孝という字は、言うまでもなく老、先輩・長者に子を合わせたものであります。
ー中略ー
疎隔・断絶に全く反対の、連続・統一を表わす文字がこの孝という字です。老、即ち先輩・長者と子、即ち後進の若い者とが断絶することなく、連続して一つに結ぶのである。そこから孝という字ができ上がった。そうして先輩・長者の一番代表的なものは親であるから、親子の連続・統一を表わすことに主として用いられるようになったのである。人間が親子・老少、先輩・後輩の連続・統一を失って疎隔・断絶すると、どうなるか。個人・民族の繁栄は勿論のこと、国家・民族の進歩・発展もなくなってしまう。
ー中略ー
教育とは何ぞやと言えば、つまるところは先輩・後輩と長者・少者の連続・連結の役目をなすものでなければならない。
要するに孝という字は、単に親を大事にして、親に尽くすという意味だけではなくて、親子・老少、先輩・後輩の連続・統一を表わす文字である。
『論語に学ぶ』 安岡正篤 PHP文庫
ということでした。
今までのことは置いておいて、これから社会をつくりなおすとすると、この『孝』という考え方がないと統一できなくなるなという気がしています。自分の経験でもそうで、いろんな人がいろんなことを言う世界ですから、ますますわからなくなるということ。そうした中で、どう取捨選択するかとか、生きていくうえでのヒントを必死に拾い集めていくしかなかったのが自分の人生でした。今は、経験を自伝や私小説を書く中で、リカバリーストーリーという形に統合できたと思っています。
世代間の連続性というのがあれば、私の人生はより簡単になっていたと思います。それは、親からの教えであるとか、先輩からの教えであるとか、老人からの教えであるとか、教師からの教えであるとか、地域住民からの教えであるとか、書籍を書いてくださった方からの教えであるとか、仕事の上司からの教えであるとか。
自分の人生ではそういったものが希薄だったような気がします。全くもって教えの不足した状況で社会に出たらそりゃ怖いだろ、と思いました。生きる知恵の学び合いができていないことが、もしかしたら、自殺が増えている原因の一つなのかもしれないなと思いました。だからこその親子間での教育や、先輩、後輩間での教え合い、老人の生きた時代の智慧とか、書籍を書いた賢人の智慧とか、会社の上司から教えてもらう社会のしきたりだとかを教え合いながら、寄り集まって学び合う場があればいいなと思っています。
他の人はどうか知りませんが、私は、かろうじてつながっている状況だと思います。だから、自分が学んだことについて、学んでいることについて、そういうものは答えではないにせよ、ヒントになるかなと思って書いていこうと思います。
親も、家族も、友人も、老人も、上司も、先輩も、後輩も、子供も、共に学びあえることができる環境は揃うと思うので、安心して自分にできることをしていきたいと思います。
2025/06/13 0:05:50 キクシェル

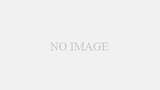
コメント